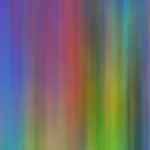神社本庁や神道の基礎知識
「神社本庁とは?」
「神社本庁の歴史が知りたい」
「神道ってなに?」
神社本庁と言われるところがありますが、これは伊勢神宮を中心とする組織の1つになります。
神社の歴史は非常に古いですが、その代表的な神社と言われるのが伊勢神宮と言われるわけです。
神社の中の神社が伊勢神宮といっても言い過ぎではありません。
例えるならば、日本にある銀行のすべての統括をしている銀行が日本銀行と呼ばれるとこですが、このイメージに近いものと考えておきましょう。
関連情報
神社本庁とは
神道の葬儀 神葬祭について– 流れ・マナー
目次
江戸時代には仏教と日本神道の2種類が信仰されてきた
日本には、たくさんの神社が存在しますが、この歴史は非常に古いと言われています。
まず最初の段階で、江戸時代に遡るはたいていの神社はその頃に出来上がっていることが理解できるでしょう。
江戸時代には、仏教と日本神道の2種類のものが信仰されてきました。
正式に言えば日本神道と言うのは宗教ではありませんが、わかりやすくするために宗教の1種としてここでは考えます。
日本神道と言うのは宗教ではない理由があり、それは教祖と呼ばれる人が存在しないからです。
昔から日本で信じられていたものがそこに集まっており、現在も日本人の生活の中で当たり前にあるものが、日本神道の考え方といえます。
例えば、日本人の1月1日やお正月付近に初詣に行くのは、この考え方の流れと言って良いでしょう。
そしてそこで願い事をするのもまたその考え方の表れとも言われています。
神様を信じている人が多いのも、世界では日本だけではありませんが日本には8,000,000の神様がいると言われており、これもその考え方の中心にあります。
人間は見たものを信じるが見えないものは信じない
よく考えたら面白いわけですが、人間は見たものを信じますが見えないものは信じない傾向にあります。
例えば、白いカラスがいるどいて信じない人も多いかもしれません。
ところが神様に関しては、なぜかいることを信じてしまう人の方が、良いわけです。
それにもかかわらず、1度も見たことがないと言うのはなんだかおかしな話かもしれません。
いずれにしても、日本人の中に埋まって馴染んでおり、深い歴史がありますので、伊勢神宮や神社を語るときに、神様の存在を抜かして語ることができません。
同じように、江戸時代には伊勢もうでなどが盛んに行われていました。
また山に登ることも、信仰の1つとして知られていたわけです。
山には神様がおり、症状で手を合わせるなどの考え方もあったわけです。
現在でも、山の頂上には鳥居などがあり神社がありますが、やはり神様と深い関係があるといえます。
広島の宮島などは海に大きな赤い鳥居が存在している
海に鳥居があるのを見たことがある人も多いでしょう。
例えば広島の宮島などは海に大きな赤い鳥居が存在しています。
なぜ海の上にあるのかといった問題もありますが、やはり神様は海にも宿っていると考えられているわけです。
もちろんそこに厳島神社と言う神社があることが理由ですが、どこにでも神様がいることを表した良い事例かもしれません。
笑いの神様と言うのを、存在しており実際にほんとにいるかどうかわからないですが日本人の中にうまく溶け込んだ言葉の1つです。
お笑い芸人等で話題の神様が降りてくるなどと言い方をしますが、そのようなところにも古くからの考え方があるわけです。
私は神社に戻すと、神社そのものは既に1000年以上昔からありますが、身近なところにあるのは江戸時代からあるものとされています。
江戸時代には、仏教と日本神道の両方が進行されていたわけですが、これはお寺と言うものに属しながら神社にも手を合わせていると言う日本人特有の考え方がそこにあります。
お寺を一方的に排除してしまうと、仏教徒が反乱を起こすため、仏教も信仰していながら、昔からある神様に調和をすると言う行為を行ったわけです。
伊勢神宮の神様はアマテラス大神
初詣に行くときには神社に行き、お墓参りをするときにはお寺に行く日本人の習慣は江戸時代位からできてきたのでしょう。
村には必ず1つのお寺と神社が存在しますが、確かに今の時代も家の周りには必ず神社とお寺があることが理解できます。
ただその中で最も古いと言われているのが伊勢神宮と呼ばれるところで、明確にはいつできているのかよく分かりません。
2000年位前からあったようですが、現在の形とは少し違ったものになります。
それ以上古いものとしては、アマテラス大神と呼ばれる神様がおり、伊勢神宮の神様は何かと聞かれたらアマテラス大神と答えるのが普通です。
同じように出雲大社と呼ばれるものもありますが、こちらはアマテラス大神ではなく大国の主の大神と呼ばれており、日本の国を作った1人として知られています。
もちろん伝説上の人ですが、本当に存在したかどうかと言われれば存在したと言っても良いかもしれません。
この辺は、その国の教育がよくわかる部分といえます。
まとめ
特に時代が降りすぎますので、写真なども残されているわけではなく、それを生したものも600年代に書かれた古事記などが中心となっています。
ちなみに、伊勢神宮に行くためには、昔は歩いて行ったようですが最近は新幹線などを使い、近鉄を用いていく流れが基本となっています。
最終更新日 2025年7月8日 by yumeka