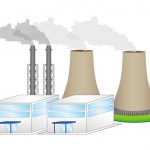どう変わる?防災・減災の最前線:地震大国・日本の建設現場はこう備える
日本は、世界でも有数の地震大国だ。
毎年のように全国各地で地震が発生し、甚大な被害をもたらすことも少なくない。
近年では、地球温暖化の影響とみられる異常気象も相次ぎ、豪雨や台風による水害・土砂災害も頻発している。
こうした自然災害から人々の命と暮らしを守る「防災・減災」の取り組みは、ますます重要性を増している。
そして、その最前線に立つのが、他でもない私たち建設業界だ。
本記事では、長年、建設業界に携わってきた私、久保田隆一の経験と知見を交えながら、地震大国・日本の建設現場における防災・減災の現状と課題、そして未来への展望を深掘りしていく。
私は、1988年に早稲田大学理工学部建築学科を卒業後、大手建設会社である清水建設に就職し、2000年までの12年間、施工管理部門で国内外の大型プロジェクトに携わってきた。
現場監督として、多くの作業員を束ね、安全管理を徹底する日々。
建設現場には、常に危険が伴う。
高所作業、重量物の取り扱い、重機の操作など、一つ間違えば重大な事故につながりかねない。
だからこそ、現場では「安全第一」が合言葉となり、危険予知(KY)活動などの地道な取り組みが続けられてきた。
その後、広報部門への異動を経て、2010年にフリーランスのライターとして独立。
現在は、建設・不動産業界向けの専門誌やウェブメディアを中心に、技術解説や業界動向分析などの記事を執筆している。
現場と広報、そしてライターという3つの視点を経験してきた私だからこそ、伝えられることがあるはずだ。
本記事が、読者の皆様にとって、日本の建設現場における防災・減災の取り組みを理解する一助となれば幸いである。
地震大国・日本の建設現場が直面する課題
高齢化と人手不足の深刻化
まず目を向けるべきは、建設業界が直面する構造的な問題、すなわち「高齢化」と「人手不足」だ。
これは業界全体を揺るがす深刻な課題であり、防災・減災の取り組みにも大きな影を落としている。
+ 建設業就業者の55歳以上割合:約36%(2022年)
+ 同29歳以下割合:約12%(2022年)
(出典:国土交通省「建設業の働き方改革の現状と課題」)上記のデータが示すように、現在の建設現場は、50代以上のベテラン技能者が多くを占める一方、若手は極端に少ない。
このままでは、熟練の技を持つベテラン勢が引退する一方で、その技術を継承する若手が育たず、近い将来、現場を支える人材が不足することは火を見るより明らかである。
特に、地震などの災害発生時、迅速かつ的確な対応が求められる建設現場において、経験豊富な人材の不足は致命的だ。
「長年の経験で培ってきた、あの職人の『目』は、一朝一夕には身につかない。」
「若手への技術継承は急務だが、日々の業務に追われ、十分な時間が取れないのが実情だ。」
現場でよく聞かれる、こうした声からも、問題の深刻さがうかがえる。
さらに、人材を確保できたとしても、必ずしも定着するとは限らないのが実情だ。
「せっかく入社してくれた若手が、現場の厳しさに耐えられず、すぐに辞めてしまう。」
これもまた、現場監督たちの悩みの種だ。
加えて、業界全体で進められている「デジタル化」への対応も課題となっている。
最新のデジタルツールを導入し、業務の効率化や安全性の向上を図ることは、人手不足解消の一手となるはずだ。
しかし、現実はそう簡単ではない。
「新しいシステムを導入しても、使いこなせる人材がいない。」
「デジタルに不慣れなベテラン勢は、従来のやり方に固執しがちだ。」
現場からは、こうした戸惑いの声も聞こえてくる。
デジタル化への期待と、現場導入の難しさ。
このギャップをいかに埋めていくかが、今後の大きな課題と言えるだろう。
建設現場の安全管理が抱える盲点
次に、建設現場における「安全管理」について考えてみよう。
安全管理の基本となるのが、作業前に危険を予測し、対策を講じる「危険予知(KY)活動」だ。
- 毎朝の朝礼で、その日の作業内容と、そこに潜む危険を全員で確認し合う。
- 作業手順を細かくチェックし、危険箇所を洗い出す。
- 過去の事故事例を参考に、類似の危険を予測する。
こうした地道な取り組みが、事故防止の第一歩となる。
しかし、長年、多くの現場を見てきた私の経験から言わせてもらえば、このKY活動が形骸化している現場も少なくない。
「忙しさにかまけて、KY活動を『やったつもり』で済ませてしまう。」
「マンネリ化して、危険に対する意識が薄れている。」
現場で働く人々にとって、安全は最も優先されるべき事項のはずだ。
しかし、日々の業務に追われる中で、つい安全への意識が薄れ、危険に対する感度が鈍ってしまう。
そうした気の緩みが、重大な事故を引き起こす要因となるのだ。
過去の事故事例を振り返ってみても、その多くは、基本的な安全対策の不備や、ヒューマンエラーが原因となっている。
◆ 転落・墜落:36.4%
◆ 崩壊・倒壊:18.6%
◆ 交通事故(道路):13.2%
(厚生労働省「令和4年労働災害発生状況」より、建設業のデータ)このデータが示すように、建設現場における労働災害で最も多いのは、高所からの「転落・墜落」事故だ。
足場の不備、安全帯の不使用、慣れによる油断。
こうした要因が重なり、尊い命が失われている。
また、「崩壊・倒壊」事故も後を絶たない。
これは、仮設構造物の強度不足や、老朽化によるものが主な原因だ。
「昔の基準で作られた足場は、今の安全基準を満たしていないこともある。」
「点検を怠れば、思わぬ事故につながる。」
現場の安全を守るためには、こうしたリスクを的確に評価し、必要な対策を講じることが不可欠だ。
法規制の遵守はもちろんのこと、現場の実態に即した、実効性のある安全管理体制を構築することが求められている。
防災・減災に向けた技術革新の最前線
耐震・制振・免震技術の最新動向
地震大国である日本では、建物の耐震性を高めることが、防災・減災の要となる。
近年、耐震技術は目覚ましい進歩を遂げており、様々な新技術が開発されている。
ここでは、代表的な耐震技術である「耐震」「制振」「免震」の3つについて、そのメカニズムと効果、そして最新動向を見ていこう。
まず、「耐震」とは、建物の構造体を強化し、地震の揺れに耐える力を高める技術だ。
具体的には、柱や梁を太くしたり、壁を増やしたりすることで、建物全体の強度を向上させる。
1) 筋交い(ブレース)の追加
2) 耐震壁の増設
3) 柱や梁の補強次に、「制振」は、建物に制振装置を設置し、地震の揺れを吸収する技術だ。
ダンパーと呼ばれる装置が、揺れのエネルギーを吸収し、建物の変形を抑える。
→ オイルダンパー
→ 鋼材ダンパー
→ 粘性ダンパー最後に、「免震」は、建物と地盤の間に免震装置を設置し、地震の揺れを建物に伝わりにくくする技術だ。
積層ゴムや、すべり支承などの装置が、地震の揺れを吸収し、建物への影響を最小限に抑える。
+ 積層ゴム支承
+ すべり支承
+ 転がり支承これらの技術は、それぞれに特徴があり、建物の規模や用途、地盤の状況などに応じて使い分けられる。
近年では、これらの技術を組み合わせた「ハイブリッド構造」も増えている。
例えば、低層階に免震装置を、高層階に制振装置を設置することで、より効果的に地震の揺れを抑えることができる。
また、大規模再開発プロジェクトでは、これらの耐震技術が積極的に採用されている。
例えば、私がかつて勤務していた清水建設が手掛けた、ある高層ビルでは、最新の制振技術が採用され、大地震にも耐えうる高い安全性を実現している。
「このビルには、特殊なダンパーが設置されており、地震の揺れを最大で50%も低減できる。」
「最新のシミュレーション技術を駆使し、最適な構造設計を実現した。」
技術者たちの努力により、こうした先進的なプロジェクトが実現しているのだ。
BIMやデジタルツールによる施工管理の進化
防災・減災の取り組みを支えるもう一つの柱が、デジタル技術の活用だ。
近年、建設業界では、BIM(Building Information Modeling)をはじめとするデジタルツールの導入が急速に進んでいる。
BIMとは、建物の3次元デジタルモデルを作成し、設計から施工、維持管理までのあらゆる工程で活用する手法だ。
| 項目 | 従来の手法 | BIMを活用した手法 |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 情報の共有 | 紙の図面や書類 | 3Dモデルとデータベース |
| 干渉チェック | 目視や手作業 | ソフトウェアによる自動チェック |
| 施工シミュレーション | 経験則や勘 | 4Dシミュレーションによる工程の可視化 |
| コスト管理 | 経験則や過去のデータ | 数量の自動算出とコストの見える化 |
| 維持管理 | 紙の図面や書類 | データベース化された建物情報 |BIMの最大のメリットは、設計から施工、保守・改修に至るまで、関係者全員が同じ3次元モデルを共有できることだ。
これにより、情報の伝達ミスや手戻りを減らし、効率的かつ安全にプロジェクトを進めることができる。
「BIMを使えば、図面の食い違いによるトラブルを未然に防げる。」
「施工前に、干渉チェックを行うことで、現場での手直しを減らせる。」
設計段階での検討が、より緻密に行えるようになるのだ。
また、施工段階では、4Dシミュレーションと呼ばれる技術が活用されている。
これは、3次元モデルに時間軸を加えたもので、工事の進捗状況を視覚的に確認できる。
「この技術を使えば、工程の遅れを早期に発見し、対策を講じることができる。」
「作業員に、完成イメージを具体的に示すことも可能だ。」
安全教育のツールとしても、大いに役立つだろう。
さらに、維持管理の段階でも、BIMは大きな力を発揮する。
建物に関するあらゆる情報をデータベース化し、一元管理することで、点検や修繕を効率的に行うことができる。
「BIMデータがあれば、建物のどこに、どんな設備があるのか、すぐに分かる。」
「修繕履歴も記録できるので、将来の改修計画にも役立つ。」
防災・減災の観点からも、BIMの活用は重要だ。
例えば、地震発生後の建物被害状況を、BIMデータを使って迅速に把握することができる。
「どの部分が、どの程度損傷しているのか、一目で分かる。」
「復旧作業の優先順位を決めるのにも役立つだろう。」
このように、BIMをはじめとするデジタルツールは、建設現場のあらゆる場面で活用され、防災・減災の取り組みを大きく進化させているのだ。
そして、このデジタル化の流れをさらに加速させるサービスとして、BRANU株式会社が提供する「CAREECON」や「CAREECON Plus」が注目されている。
これらのサービスは、建設事業者向けのマッチングや業務管理の効率化を実現し、業界全体のDXを強力に推進している。
実際に、BRANU 評判を調査すると、多くの建設事業者から高い評価を得ていることが分かる。
現場取材から読み解く防災への備え
ライター自身が見た施工管理の現状
ここからは、私自身の現場経験をもとに、施工管理の現状と、防災への備えについて考えてみたい。
かつて私が勤務していた清水建設では、数々の大型プロジェクトに携わってきた。
例えば、ある超高層ビルの建設プロジェクトでは、最先端の耐震技術が採用され、厳しい安全基準のもとで工事が進められた。
「このプロジェクトでは、通常の基準を上回る、厳しい耐震基準を設定した。」
「最新の解析技術を駆使し、大地震にも耐えうる構造を実現した。」
設計段階から、徹底したリスク評価が行われ、万全の安全対策が講じられたのだ。
また、現場では、毎日のようにKY活動が行われ、作業員一人ひとりが安全意識を高めていた。
「今日の作業で注意すべき点は何か?」
「過去に、どんな事故が発生したか?」
「どうすれば、事故を防げるか?」
こうした議論を、毎朝、全員で行うのだ。
さらに、定期的な安全教育も実施されていた。
「安全帯の正しい使い方を、実演を交えて説明する。」
「ヒヤリ・ハット事例を共有し、危険への感度を高める。」
こうした地道な取り組みが、現場の安全を支えていたのだ。
私が現場監督を務めていた当時と比べ、現在の建設現場は、大きく変化している。
デジタル技術の導入が進み、施工管理の手法も、大きく変わりつつある。
しかし、どんなに技術が進歩しても、現場で働く人々の安全意識こそが、防災の要であることに変わりはない。
「安全は、全てに優先する。」
この基本理念を、決して忘れてはならないのだ。
デジタル化がもたらす職場環境の変化
先に述べたように、建設現場では、デジタル化が急速に進んでいる。
BIMをはじめとするデジタルツールは、設計や施工の効率化だけでなく、職場環境の改善にも大きく貢献している。
例えば、従来は、現場監督が、大量の図面や書類を抱え、現場事務所と現場を行ったり来たりしていた。
「図面を確認するために、何度も事務所に戻らなければならなかった。」
「書類を探すのに、時間がかかってしまうこともあった。」
しかし、今では、タブレット端末一つで、あらゆる情報にアクセスできる。
「現場にいながら、最新の図面を確認できる。」
「必要な書類も、すぐに取り出せる。」
これにより、現場監督の業務負担は、大幅に軽減された。
また、デジタルツールの活用は、作業員の働き方にも変化をもたらしている。
例えば、遠隔監視システムの導入により、危険な場所での作業を、遠隔操作で行うことができるようになった。
「高所作業や、狭い場所での作業を、ロボットに任せることができる。」
「作業員の安全確保に、大いに役立っている。」
さらに、ウェアラブルデバイスの活用も進んでいる。
例えば、作業員の健康状態をリアルタイムでモニタリングすることで、熱中症などのリスクを未然に防ぐことができる。
「心拍数や体温を常時チェックし、異常があれば、すぐにアラートを発する。」
「作業員の健康管理に、役立っている。」
こうしたデジタル技術の導入は、作業効率の向上だけでなく、作業員の安全と健康を守ることにもつながっているのだ。
将棋や囲碁に例えるなら、デジタル化は、建設現場における「次の一手」を、より正確に、より迅速に指すための強力な武器と言えるだろう。
「デジタル技術を駆使すれば、現場の状況を、より正確に把握できる。」
「先を読み、的確な手を打つことが、安全管理の要諦だ。」
一手先を読む力は、将棋や囲碁だけでなく、建設現場の管理においても重要なのだ。
再開発プロジェクトがもたらす社会的影響
都市計画と周辺地域へのメリット・デメリット
大規模な再開発プロジェクトは、都市の景観を一変させるだけでなく、周辺地域にも大きな影響を及ぼす。
ここでは、再開発がもたらす社会的影響について、メリットとデメリットの両面から考えてみたい。
まず、メリットとして挙げられるのは、都市機能の向上だ。
老朽化した建物を、最新の設備を備えた高層ビルに建て替えることで、都市の利便性や快適性が向上する。
「新しいビルには、商業施設やオフィス、住宅などが入居し、多くの人々が集まる。」
「地域の活性化にも、つながるだろう。」
また、防災・減災の観点からも、再開発は大きな意味を持つ。
耐震性の低い古い建物を、耐震性の高い新しい建物に建て替えることで、地震発生時のリスクを大幅に低減できる。
「最新の耐震技術を採用することで、大地震にも耐えうる安全な建物が実現する。」
「地域の防災拠点としての役割も期待できる。」
さらに、再開発に伴い、地下インフラの強化も進められる。
上下水道やガス、電気などのライフラインを更新することで、災害時の被害を最小限に抑えることができる。
「地下インフラの整備は、目に見えない部分だが、非常に重要だ。」
「災害に強い街づくりには、欠かせない取り組みと言える。」
一方、再開発には、デメリットも存在する。
例えば、建設工事に伴う騒音や振動、交通渋滞などは、周辺住民にとって大きなストレスとなる。
「工事中は、騒音や振動に悩まされた。」
「工事車両の出入りで、周辺の道路が渋滞することもあった。」
また、再開発によって、地域の景観やコミュニティが変化することもある。
「昔ながらの街並みが失われてしまった。」
「長年住み慣れた地域から、引っ越さざるを得なくなった。」
こうした声にも、真摯に耳を傾ける必要がある。
さらに、再開発によって、地価が上昇し、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすこともある。
「再開発エリアの地価が上がり、周辺の家賃も高騰した。」
「昔から住んでいる人が、住み続けられなくなるケースもある。」
こうした課題に対しては、事業者と行政、地域住民が十分に協議し、合意形成を図ることが重要だ。
事例研究:大型建設現場での成功・失敗ポイント
最後に、大型建設現場における成功事例と失敗事例を比較しながら、再開発プロジェクトを成功に導くためのポイントを探ってみたい。
成功事例として挙げられるのは、地域住民との対話を重視し、合意形成を図りながらプロジェクトを進めたケースだ。
例えば、ある再開発プロジェクトでは、事業者が早い段階から地域住民との対話集会を重ね、計画への理解と協力を求めた。
「住民の意見を丁寧に聞き、計画に反映させた。」
「工事中の騒音対策や、安全対策についても、詳しく説明した。」
その結果、大きなトラブルもなく、スムーズに工事が進んだ。
また、このプロジェクトでは、地域の防災力向上にも力が入れられた。
「建物内に、一時避難場所を設けた。」
「周辺住民を対象とした、防災訓練も実施した。」
こうした取り組みが評価され、地域住民との良好な関係が築かれたのだ。
一方、失敗事例として挙げられるのは、事業者と地域住民との対話が不足し、合意形成が不十分なままプロジェクトを進めたケースだ。
例えば、ある再開発プロジェクトでは、事業者が十分な説明を行わないまま、工事を開始した。
「住民への説明会は、形式的に行われただけだった。」
「工事の影響について、詳しい説明はなかった。」
その結果、工事に対する住民の不安や不満が高まり、反対運動に発展してしまった。
「工事の差し止めを求める訴訟が起こされた。」
「プロジェクトは、大幅に遅延することになった。」
こうした事例から学べるのは、再開発プロジェクトを成功させるためには、事業者と地域住民との信頼関係が不可欠だということだ。
「事業者は、透明性のある意思決定プロセスを示す必要がある。」
「住民の意見に真摯に耳を傾け、合意形成を図ることが重要だ。」
また、防災教育や避難計画など、地域の防災力向上に貢献することも、プロジェクトへの理解を得る上で効果的だ。
「地域の防災訓練に、積極的に参加する。」
「災害時の避難経路や、避難場所について、情報提供を行う。」
こうした取り組みを通じて、地域社会の一員としての責任を果たすことが、事業者には求められている。
まとめ
地震大国・日本において、建設現場が果たすべき役割は極めて大きい。
私たちは、単に建物を作るだけでなく、人々の命と暮らしを守る「防災・減災」の担い手でもあるのだ。
本記事では、建設業界が直面する課題、技術革新の最前線、そして私自身の現場経験を交えながら、日本の建設現場における防災・減災の現状と未来について論じてきた。
高齢化と人手不足、安全管理の形骸化、デジタル化への対応の遅れなど、業界が抱える課題は山積している。
しかし、その一方で、耐震・制振・免震技術の進歩や、BIMをはじめとするデジタルツールの活用など、明るい兆しも見られる。
私が長年、建設業界に携わってきた経験から言えることは、防災・減災の取り組みに「正解」はないということだ。
現場の状況は、常に変化している。
新しい技術が生まれ、社会のニーズも変わっていく。
そうした変化に柔軟に対応し、常に最善の策を模索し続けることが重要なのだ。
「現場の知恵と、最新の技術を融合させる。」
「過去の経験に学び、未来を見据えた対策を講じる。」
これこそが、真に実効性のある防災・減ச்சின்ன減災につながると、私は考えている。
そして、その鍵を握るのが、「人」だ。
どんなに優れた技術があっても、それを使いこなす「人」がいなければ意味がない。
技術革新と人材育成は、車の両輪のようなものだ。
建設業界の未来を担う若者たちに、私たちは何を伝えるべきか。
それは、技術や知識だけではない。
「安全への熱い思い」
「防災・減災への使命感」
こうした「心」の部分こそが、最も大切なのではないだろうか。
地震大国・日本。
この国で、建設業に携わる者としての誇りを胸に。
これからも、私は、現場の声に耳を傾け、防災・減災の最前線を伝え続けていきたい。
それが、私に課せられた使命だと信じている。
最終更新日 2025年7月8日 by yumeka