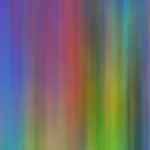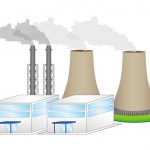朋和産業に聞いた。環境保全のために生活排水を少なくする
目次
1.朋和産業が環境保全の為に考えていることとは?
環境保全は国や企業が莫大なお金をかける価値があることですが、規模が大きいからといって個人レベルでは何もできないわけではありません。
一人ひとりが環境を意識した行動を取れば、積み重ねで大切な地球の資源を守ることができます。
日本は水資源が豊富で水はタダで無限に利用できると考えている人もいます。
しかしそれは間違いで飲めるほど安全な水には限りがあり、世界では安全な飲料水の確保に困る地域がたくさんあります。
水道から流れる水は、雨水や川の水からできています。
そのままだと不衛生で飲むには不安があるため、浄水場で塩素を入れてアンモニアなどの汚れを除去し飲めるようにします。
使用され汚れた水は下水道管から水再生センターに運ばれ川や海に流されます。
それらが再び飲料水へと変わるという工程が毎日行われています。
当たり前のように水道から流れてきますが、循環しながら利用しているためできるだけ無駄にせず汚さないことが環境保全に繋がると朋和産業は言及しています。
まだ環境保全の意識が薄かった頃、水質汚染は産業排水によるものでした。
工場から排出された有害物質を含む水を飲み様々な症状が出るという公害が起きたため、政府は規制をかけて被害の拡大を防ぎました。
現在は公害の心配はほとんどありませんが、各家庭で排出される生活排水が汚染原因の大部分を占めるようになりました。
現代人は食べ残しを簡単に排水口に捨ててしまいがちで、し尿を含めると1日に1人当たり250リットルも汚水を捨てているという計算です。
その中に汚れは40g、排出の制限ができないし尿を除くと汚れは27g出ています。
たったの27gでも一人ひとりの量が集まれば大変な量になることは明白で、少しだからと排水口に食べ残しを流すのは危険です。
2.安全な水を飲むためには食べ残しをしないよう食事を作りすぎない
味噌汁に含まれる窒素やリンは伊勢湾のような水の出入りが緩やかな場所においてはプランクトンを増やす原因となります。
プランクトンの異常増殖は赤潮を引き起こし魚を激減させます。
味噌汁1杯の中に魚が棲息することはもちろんできません。
この状態から魚が安全に生活できるようにするには、浴槽5杯分もの水が必要です。
マヨネーズ大さじ1杯では12杯分、天ぷら油は330杯分もの量になります。
生活排水は最終的には魚が棲む海や川に流されるので、自分たちが知らないところでたくさんの水が汚水をきれいにするために使われていることが分かります。
安全な水を今まで通り飲むためには、できるだけ食べ残しをしないように食事は作りすぎを避けることが大切です。
もし残ってしまったら新聞紙など吸水性の高い紙に吸わせて排水口に流す量を極力減らします。
揚げ物やラーメンの器は完食しても油がたくさん残っています。
これもすぐに流すのではなく、キッチンペーパーで油を拭き取るようにします。
油を拭き取ることは、その後の食器洗いが楽になり洗剤の使用量も減ります。
洗剤は油汚れを落とすために強力な成分を配合しているため環境にはあまり良くありません。
量をたくさん使っても洗浄力に違いは出ないので、メーカーが記載する量に従いましょう。
3.キッチンの排水口に器具を取り付け生活排水を汚さないようにする
キッチンの排水口にはストレーナーという網状の器具を取り付けます。
これは固形物が網に引っかかる仕組みとなっており、排水汚れが30%も軽減されます。
排水口が小さすぎてストレーナーが利用できない場合、水切りネットや使えなくなったストッキングなどで代用できます。
米の研ぎ汁はラーメンの汁などと比べれば汚れていないように見えますが、実際は魚が棲めるようにするには浴槽6杯分も必要です。
ラーメンの汁が浴槽4杯分なので、米の研ぎ汁の方が環境への影響が大きいと考えられます。
しかし米の研ぎ汁には再利用法があり、植物の水やりに使えます。
米ぬかが入っているので栄養素を多く含み、リンやカリウムなどのミネラル類を多く含みます。
研ぎ汁だけを肥料として植物を育てるのは難しいですが、2日~3日に1回程度であれば虫やカビの心配もなく再利用できます。
4.環境保全のためにトイレやお風呂場でも節水を心がける
さらにキッチンの他にもトイレやお風呂場で生活排水対策は可能です。
トイレを我慢するのは現実的ではありませんが、流れる水の量を少なくするのは生活に支障が出ません。
方法はロータンクの中に水を入れたペットボトルを入れるだけで、2リットルペットボトルを入れれば2リットル分が節水できます。
最近はメーカーでも節水型トイレを開発しており、従来のトイレより8リットルほど少ない水が流れます。
お風呂では浴槽の水を洗濯や洗車に再利用しましょう。
1年間で180リットル~200リットルもの量を浴槽に貯めているとされ、再利用できれば2リットルペットボトルが3万本以上になります。
全てを再利用できなくても、できるところから始めるのが大切です。
シャワーについては流しっぱなしを止めると節水に効果的です。
3分間の流しっぱなしを回避できれば36リットルの水を使わずに済みます。
節水は光熱費の節約と環境保全を両立できるため実践しやすいと朋和産業はアドバイスしています。
最終更新日 2025年7月8日 by yumeka