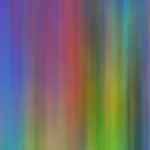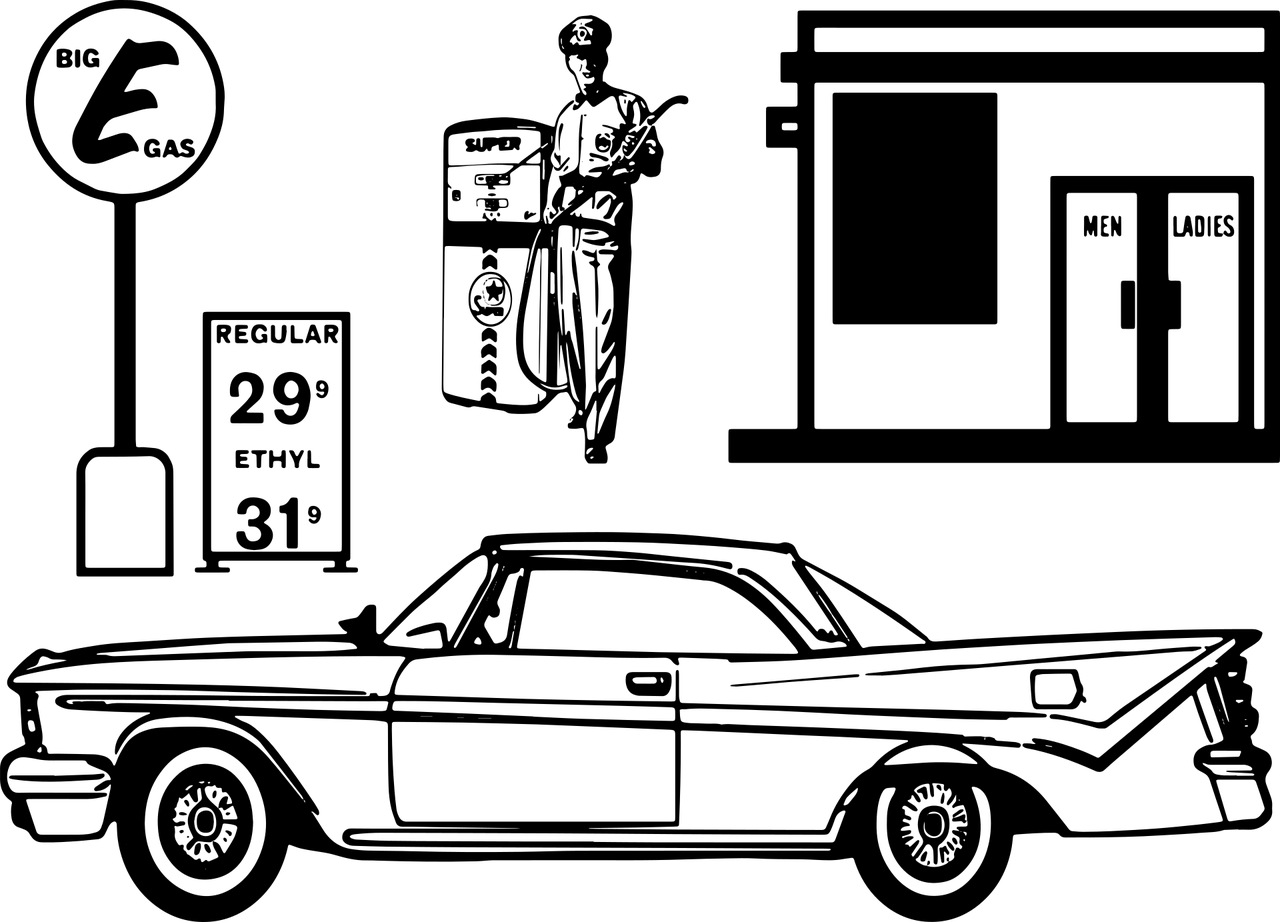
石油高騰は企業を圧迫あと何年もつのか
1)石油価格が上がるとどうなる?
石油価格が上がると製品価格に上乗せされて消費者の購買意欲を下げたり、企業の収益を圧迫して設備投資や雇用環境を悪化させたりして、経済にも影響します。
一般的に特定商品の高値が続けば消費者は買い控える、代替品を買うなどしますが灯油やガソリンなどの石油製品はストーブや自動車といった専用機器で使用する生活必需品であるため、使わない買わないと即座に選択することは難しいといえます。
化石燃料への依存体質が変わらない限り、原油の高騰を生活者個人の知恵で乗り切ることはできないでしょう。
石油はどうして化石燃料と呼ばれるのでしょうか。
これは堆積したプランクトンやバクテリアの遺骸が、100万年以上という長い年月をかけて炭化水素に分解されたものだと考えられるからです。
つまりプランクトンやバクテリアの化石が、石油だというわけです。
バクテリアやプランクトンなどの生物遺骸が地中の奥深くに埋もれて、100万年以上かけて油母というワックス状の高分子化合物になり、さらに長い時間をかけて高圧、高熱で分解され液体や気体の炭化水素になったという考え方です。
この説の根拠は葉緑素が変化したと考えられるポリフィリンや、コレステロールが変化したと考えられるステランなどが原油に含まれていることが挙げられています。
2)石油はどのようにして採掘されるのか?
しかし原油は地球上のどこにでも存在するわけではありません。
太古の昔海底や湖底だった場所に、土砂が堆積し油母を多く含む貯留岩になります。
貯留岩の上に地層が積み重なり、地中の奥深くで油母が熱分解されてできた炭化水素は圧力によって上へと浸透して、原油をためるのに適した岩へと移動していきます。
貯留岩へと集まってきた炭化水素は周囲が油を通さない性質の岩で覆われているトラップと呼ばれるエリアへと、移動集積していきます。
これが油田やガス田となるのです。
産油地帯といわれる地域には、このような複雑な条件が整っているのです。
原油が多く発見されるのは約2億5000万年から6500万年前の地層ですが、炭化水素が移動集積することから原油ができた年代が周囲の地層と必ずしも一致しないという考え方もあります。
そこで生物から作られた油に地球内にもともとあった炭素が捕捉されて、原油ができたという説もあります。
これは原油の分布と生物の分布が明らかに異なっている点、世界各地で産出される原油がほぼ同一の組成である点などを根拠としています。
太陽系のほかの惑星にもメタンガスなど大量の炭素があることがわかっていますが、惑星ができた当初から地球にあったメタンが地中深く閉じ込められて原油の材料になっているとすれば、原油や天然ガスの埋蔵量に限りがあるという定説が根底から覆されることになるでしょう。
3)石油はいつか枯渇するのか?
またこの説の中には、地球の内核で放射線の作用により炭化水素が発生するという新説もあります。
どの説が正しいにせよ石油がどうやってできたかという問題は、世界経済にもかかわる重要性がありこれからのエネルギー問題を考えるうえで切り離せない問題です。
省エネルギー、脱油、新エネルギー開発の必要性が世界で声高に叫ばれていますが、現在でもエネルギーの大半は化石燃料に依存しています。
その化石燃料とウランには埋蔵量に限りがあるとする説が主流です。
このまま採掘を続けていたらいつかは枯渇してしまうという認識は世界共通です。
ただいつ枯渇するかという推測は、報告される数字にばらつきがあります。
化石燃料があとどれくらい残っているのかを正確に把握することは、難しいです。
現在確認推定されている採取可能な量を確認可採埋蔵量または供給可能量と呼びます。
これは地下数千メートルもの奥深くにある化石燃料の存在量を、様々な方法で推定計算した数字であって実際に計測した数字ではありません。
また供給可能量は、現在の価格と技術の水準で経済的に採取できると推算された量でもあります。
地下に埋蔵されている量から採取できる量は、実際には技術的にもコストの面でも限られているのです。
石油の場合、地下の貯留岩から採取できる回収率は世界平均で28%と報告されています。
確認埋蔵量を現在の1年間の供給量で割った数字を、可採年数といいます。
今の消費ペースで採取続けたら何年もつのかという目安になります。
4)まとめ
資源エネルギー庁が発行している日本のエネルギーによれば30年後までは供給可能とされています。
この数字はあくまでも現在の消費ペースに基づいたもので、今後の予測値は入っていません。
つまり今後大規模な油田が開発されたり大幅な技術革新があって省エネが進んだり、中国やインドなどアジア諸国の経済発展に伴い原油の消費量が増加するといった要素は、計算に入ってはいません。
ほかの化石燃料では石炭は145年後まで、天然ガスは55年後まで供給可能とされています。
石炭の供給可能量にはまだまだ余裕があるように見えますが、原油に比べ燃焼したときにより多くの二酸化炭素が発生するため地球温暖化防止の面からあまり大量に使用しないほうが良いと考えられています。
最終更新日 2025年7月8日 by yumeka