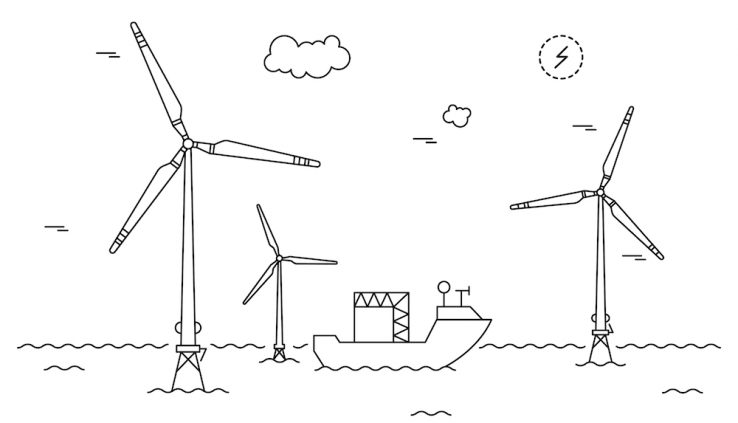
洋上風力などほかの発電方法の可能性
「原子力発電に替わる発電方法を知りたい」
「洋上風力のメリットとデメリットは?」
「Influx社の洋上風力の取り組みを調べている」
日本はエネルギー資源が乏しく、多くのエネルギーを輸入に頼っています。
最も比率の高い火力発電は天然ガスや石油、石炭などがもちいられますがそのほとんどが輸入に依存しています。
そしてこれらの化石燃料は地球温暖化の原因ともなっていますので、今後規制されていくことが想定されていて利用にはますます厳しい条件が付くことになるのです。
加えて現在日本は空前の円安の状況に陥っていて、輸入価格の高騰に歯止めがかかっていません。
今後電気代やガス料金が値上がりすことは、間違いなくますますエネルギーについて考えていかなければならなくなっています。
目次
政府が原子力発電所について再度開発を方針を打ち出している
このような中で日本ではエネルギーミクスと呼ばれる様々な発電手法を用いて、安定供給に努めようとしています。
最近では政府が原子力発電所について再度開発を方針を打ち出していて、様々な意見が出ている状況です。
政府が原子力に言及したのは、発電効率が他の代替エネルギーと比べて非常に高いことが要因です。
過去夢のエネルギーといわれ、福島第一原発事故が発生するまではそのリスクの高さに指摘する人はいても歯止めをかけるような動きはありませんでした。
そんな中円安が追い打ちをかけてしまったため、禁断の果実に手を出そうとしています。
このままでは原発事故の教訓を生かせないまま不毛だ大地だけが広がっていくことも、将来的に考えておくほうが無難です。
海に風力発電を建設する洋上風力発電
とはいっても手をこまねいているわけではなく、いろいろだな痛い手段を模索はしています。
有望なものの一つに、洋上風力発電と呼ばれるもので海に風力発電を建設するものでイギリスではすでに世界に先駆けて導入が進んでいるのです。
イギリスは島国なので海に囲まれた立地があり、建築するための環境が整っています。
世界に先駆けて導入することで自然エネルギー大国としての地位を気づくばかりか、多くの資本を取り込むといった国家的な戦略も担っているのです。
残念ながら日本ではこれらの先進的な動きはされておらず、国内の企業も数が限られているのが実情です。
とはいえ手をこまねいているわけではなく大手商社を中心に秋田県沖に建築計画を国が進めているなど徐々に浸透していますが、現在の電力を確保するためにはまだまだ時間がかかることは言うまでもないでしょう。
洋上風力発電のメリットとデメリット
洋上風力発電は海という安定した風が吹き続ける環境が整っているという点で、電気の安定供給という面でメリットが高い手段です。
一方で海洋は潮風による腐食が最大のネックであり、これらの定期的なメンテナンスが欠かせません。
また台風などの災害が多い国であるという点も、本当に安定的に供給していくためには色々と越えなければならないハードルが立ちふさがっているのです。
地中の熱を利用した地熱エネルギー
もう一つ有望な代替方法として、地熱エネルギーが挙げられます。
地熱エネルギーは地中の熱を利用した発電方法で、火山帯国日本ではすでに一部の自治体で導入がされています。
こちらも安定性に優れていて、一部の自治体ではその自治体が利用するエネルギーを自給自足できることが証明されました。
一方で小さな自治体なので実現可能だという現状はあって、利用できる場所も限られていることから日本全体を賄うまでには到底足りません。
太陽光発電はデメリットも多い
太陽光発電も進められていますが山の多い日本では平地は限られていて、しかも災害によって太陽光パネルが濁流にのまれてしまう事故も発生しています。
さらに太陽光発電パネルの有毒性や、処分といった別の課題が生まれていてなかなか十分に浸透がされていないという課題もあります。
加えて太陽光発電は日中しか発電がされないため、夜間の対応にも課題があるのがネックなのです。
最近では戸建ての住宅にこのような太陽光発電システムを導入して、個人個人が自給自足できるような取り組みが進められているスマートハウスかも徐々に脚光を浴びている状況ではあります。
このように国家や大企業といったアプローチに加えて、個々の取り組みを総動員して初めて実現できるという途方もない取り組みが必要なのです。
まとめ
時間と労力がかかる取り組みだからこそ、より簡単で発電できる原子力エネルギーに政府が方針を変えるのも一部では仕方のないことであるともいえます。
一方で核のゴミは定期的に生まれている中で、その処分場所も決まっていない状況で新しい発電所を建築することは国民の大きな抵抗があります。
現在政府は国民へ「お願い」することと、老朽化して停止していた火力発電を使って何とか乗り切っていますがこれもいつまで持つかは分かりません。
最悪の場合輪番停電のような取り組みが発生することや、需要がひっ迫する夏や冬に突然停止してしまうということもあり得ます。
商業施設などでも電力を間引くなど焼け石に水のような対応をしていますが、エネルギーミクスは喫緊の課題であり速やかに対処しないと明日が危なくなるという危機感を持って行動が必要になるということはわかると思います。
最終更新日 2025年7月8日 by yumeka









